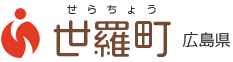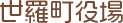本文
資格に関すること
資格に関する手続きについて
75歳になったとき
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。加入の手続は必要ありません。
75歳の誕生日の前月中に資格確認書が、1人に1枚、広域連合から郵送されます。
毎年8月1日付けで更新します。(7月下旬に広域連合から郵送されます。)
前年の所得をもとに、8月1日から翌年の7月31日までの自己負担割合を判定します。
病院等にかかるときの自己負担割合は、「1割」「2割」又は「3割」です。
自己負担割合は世帯構成が変わると(死亡、75歳年齢到達、転入、転出など。)年度途中で自己負担割合が変わる場合があります。また、所得の更正(修正)があった場合は、該当年度の8月1日に遡って変更となります。
保険料納付通知については加入から約2か月後に郵送でお知らせします。
原則特別徴収(公的年金から差引)ですが、加入したばかりの方や特別徴収の対象にならない方については普通徴収(納入書又は口座振替)での納付になります。
口座振替を希望される場合は、町税等の口座振替とは別に、後期高齢者医療保険料の口座振替の届出が必要となります。
後期高齢者医療制度の運営主体(保険者)は広島県の全市町で構成する広島県後期高齢者医療広域連合です。世羅町では申請・届出の受付、資格確認や保険料の徴収などを行っています。
制度の概要等について、詳しくは広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
65歳以上75歳未満の一定の障害のある方で、障害認定により後期高齢者医療制度へ加入を希望されるとき
加入の手続をしてください。認定後、後期高齢者医療制度に加入できます。
一定の障害とは、国民年金法等における障害年金1・2級、身体障害者手帳1・2・3級及び4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳Ⓐ・Aに該当する方です。
加入前の健康保険が健保組合等の被扶養者の場合は、保険料の軽減の手続も必要です。
保険料納付通知については加入から約2か月後に郵送でお知らせします。あらかじめ口座振替の届出をしておくことができます。
なお、有期認定の方は期限までに更新の手続が必要となります。
【申請に必要なもの】
- 障害認定申請書 [Wordファイル/49KB]
- 資格確認書又は資格情報のお知らせ
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書、転入前の障害認定証明書のうちいずれか
(更新手続で、期限までに手帳等を受取れない場合は障害認定誓約書 [Wordファイル/29KB]を提出し、受取後に提出していただきます。) - 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
障害認定の撤回を希望されるとき
後期高齢者医療制度の資格を喪失します。
資格喪失証明書を交付しますので、新たな健康保険へ加入の手続が必要となります。
【申請に必要なもの】
- 障害認定撤回申請書 [Wordファイル/42KB]
- 資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
広島県外の市区町村から転入したとき
異動(転入)の届出をしてください。
住所異動の手続の約1週間後に郵送で資格確認書等を送付します。
保険料納付通知については加入から約2か月後に郵送でお知らせします。あらかじめ口座振替の届出をしておくことができます。
【申請に必要なもの】
- 被保険者資格異動届出書 [Wordファイル/52KB]
- 転入前の市区町村が発行した負担区分証明書
- 転入前の市区町村が発行した被扶養者証明書
(転入前の市区町村で被扶養者の保険料軽減を受けていた場合) - 転入前の市区町村が発行した認定等証明書
(転入前の市区町村で75歳未満の方が障害認定により後期高齢者医療制度に加入していた場合、転入前の市区町村で特定疾病認定を受けていた場合) - 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
広島県内の市区町村から転入したとき
町内で住所が変わったとき
氏名を変更したとき
異動(転入、転居、氏名変更)の届出をしてください。
住所異動等の手続の約1週間後に郵送で資格確認書等を送付します。
転入者の方への保険料納付通知については加入から約2か月後に郵送でお知らせします。あらかじめ口座振替の届出をしておくことができます。
【申請に必要なもの】
- 被保険者資格異動届出書 [Wordファイル/52KB]
- 資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
広島県内の市区町村へ転出するとき
住所異動(転出)の届出をしてください。
旧住所の資格確認書等は転出先の市区町村に提出してください。
保険料の還付が発生する場合は還付口座の届出が必要となります。また、転出後に世羅町に居住していた期間の保険料の納入書が届く場合があります。
【申請に必要なもの】
- 被保険者資格異動届出書 [Wordファイル/52KB]
- 資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 還付口座届出書 [Wordファイル/28KB]
- 被保険者の口座を確認できるもの
- 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
広島県外の市区町村へ転出するとき
住所異動(転出)の届出及び負担区分証明申請等を提出してください。発行した負担区分証明書は転出先の市区町村へ提出してください。
資格確認書等は返却してください。
保険料の還付が発生する場合は還付口座の届出が必要となります。また、転出後に世羅町に居住していた期間の保険料の納入書が届く場合があります。
【申請に必要なもの】
- 被保険者資格異動届出書 [Wordファイル/52KB]
- 負担区分等証明申請書 [Wordファイル/38KB]
- 認定等証明書交付申請書 [Wordファイル/38KB]
(75歳未満で障害認定により後期高齢者医療制度に加入していた場合、特定疾病認定を受けていた場合、被扶養者の保険料軽減を受けていた場合) - 資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 還付口座届出書 [Wordファイル/28KB]
- 被保険者の口座が確認できるもの
- 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
広島県外の住所地特例施設に住所を移すとき
住所異動(転出)及び住所地特例の届出を提出してください。
【申請に必要なもの】
- 被保険者資格異動届出書 [Wordファイル/52KB]
- 住所地特例(該当・非該当)届出書 [Wordファイル/52KB]
- 資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 施設又は病院等の名称及び所在地がわかるもの
- 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
生活保護を受けるようになったとき
資格喪失の届出をしてください。
【申請に必要なもの】
- 被保険者資格異動届出書 [Wordファイル/52KB]
- 生活保護開始決定通知書
- 資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
生活保護を受けなくなったとき
資格取得の届出をしてください。
【申請に必要なもの】
- 被保険者資格異動届出書 [Wordファイル/52KB]
- 生活保護廃止(停止)決定通知書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
一部負担金の割合が3割で世帯(対象者)の収入状況が一定未満のとき
一部負担金の割合が3割に該当する方でも、次に該当するときには2割又は1割に変更できる場合があります。
- 同一世帯に後期高齢者医療被保険者が2人以上いる場合、総収入の合計額が520万円未満
- 同一世帯に後期高齢者医療被保険者が1人の場合は次のいずれか
(1)被保険者本人の総収入が383万円未満
(2)同一世帯の70~75歳の方を含めた総収入の合計額が520万円未満
【申請に必要なもの】
- 基準収入額適用申請書 [Wordファイル/44KB]
- 対象者の収入の状況のわかるもの
- 資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
限度額適用認定証等の新規発行終了について(資格確認書交付兼任意記載事項併記申請)
令和6年12月2日から紙の保険証の新規発行終了にあわせて、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行も終了となりました。今後は、各認定証の代わりに、申請により資格確認書へ適用区分(限度区分)を記載します。
資格確認書へ適用区分の記載を希望する場合は、次の書類を健康保険課又はせらにし支所に提出してください。資格確認書へ適用区分の記載がない場合でも、医療機関等の窓口でオンラインで資格確認をすることに同意すれば、適用を受けることができます。
【申請に必要なもの】
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [Wordファイル/46KB]
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
「マイナ保険証」や「適用区分が記載された資格確認書」を医療機関へ提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。自己負担限度額の区分については、自己負担限度額等一覧表 [PDFファイル/65KB]をご確認ください。
なお、入院したときは医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。入院時の食費・居住費について、詳しくは「入院時の食費・居住費」をご確認ください。
| 適用区分 | 高額療養費制度における自己負担限度額 の区分。 |
| 長期入院該当日 | 過去12か月の期間内における入院日数(低所得者2の区分に該当する期間に限る。)が90日を超え、認定を受けた方が適用となります。 該当する方は申請が必要です。 |
| 特定疾病区分 | 人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病などにより認定を受けた方が適用となります。 該当する方は申請が必要です。 |
長期入院該当の申請について(低所得者2の区分の方)
低所得者2の区分の方で、低所得者2の区分だった期間の過去12か月間の入院合計日数が90日を超えた場合は、長期入院該当の申請が必要となります。
長期入院該当の認定は、申請日の翌月初日からとなりますので、申請月分の食費は差額支給申請が必要です。
(当広域連合の被保険者になる以前に加入していた医療保険での入院日数は算定対象となります。)
【申請に必要なもの】
- 長期入院該当適用申請書 [Wordファイル/54KB]
- 病院等が発行する入院期間がわかる領収書等
- 資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
低所得者2の区分の方で、長期入院該当の申請をした月の食費の差額支給申請をするとき
【申請に必要なもの】
- 食事(生活)療養差額支給申請書 [Excelファイル/78KB]
- 食事代等の明細が記載してある領収書
- 振込口座の確認できるもの
- 資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病等の治療を受けるとき
次の1~3に該当する方は特定疾病療養受療証を医療機関に掲示することで、1医療機関ごとの同じ月内の窓口負担が外来・入院それぞれ1万円になります。
月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入される方は、その月に限り「加入日前の医療保険」と「後期高齢者医療保険」のそれぞれの自己負担額が2分の1の5千円になります。ただし、1日が誕生日の方は除きます。
-
人工透析を必要とする慢性腎不全の方
-
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)の方
-
抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣の定める、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者に限る。)の方
【申請に必要なもの】
- 特定疾病認定申請書 [Wordファイル/43KB]
医師の意見欄の記載は医療機関に依頼してください。なお、後期高齢者医療加入前又は転入以前に特定疾病認定を受けていた方は、その認定証又は転入前の市区町村が発行した証明書があれば医師の意見欄の記載は不要です。 - 資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
資格確認書等を破損、紛失したとき
資格確認書等を破損、紛失したときは、再交付申請をしてください。
申請に必要なものを持って健康保険課に手続に来ていただいた場合は、当日再発行してお渡しできます。
【申請に必要なもの】
- 資格確認書等再交付申請書 [Wordファイル/45KB]
- 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/33KB]
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
書類の送付先を変更したいとき
入院や入所等の理由により書類の送付先変更を希望されるときは、届出をしてください。
【申請に必要なもの】
- 送付先設定申出書 [PDFファイル/61KB]
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
※郵送で提出される場合は、申出者の身分証明書(運転免許証等)の写しの添付をお願いします。
【注意事項】
・設定にあたり、宛名には、様方などが入ります。
・広島県広島市~区~町●●番地 △△様方××様)のような表示になります。
・宛名に対象の方の氏名を載せないようにするといったことはできませんのでご注意ください。
・転居や設定が不要となったときには、設定の変更や解除を申出ください。
・申出書に記載の業務のうち、設定したい業務が複数あるときは、提出先はいずれかの担当窓口で構いません。受付をした担当から各業務担当へ申出書の回付をさせていただきます。