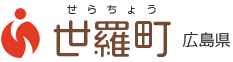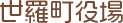本文
保険料に関すること
保険料に関すること
| リンクを押すと該当箇所に移動します |
|---|
医療費は、皆さまが病院などの窓口で支払う自己負担額と、保険から給付される医療給付費で構成されています。
この医療給付費のうち、約1割が皆さまの保険料でまかなわれています。
後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度の被保険者1人ひとりに納めていただきます。また、保険料額は前年の所得をもとに計算されます。
後期高齢者医療保険料の算定方法
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
保険料の保険料率は2年ごとに見直されます。
令和7年度の「均等割額」と「所得割率」は次のとおりです。
均等割額(49,621円)+所得割額(所得割率9.63%)=年間保険料額(限度額80万円)
所得割額=〔総所得金額等(※1)-基礎控除(※2)〕×0.0963(所得割率)
※1) 総所得金額等とは、「公的年金等収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で算出される金額のことで、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も、総所得金額等に含まれます。
※2) 地方税法に定める基礎控除額は、次のとおりです。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | ||
|---|---|---|---|
|
2,400万円以下 |
43万円 |
||
|
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
||
|
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
||
|
2,500万円超 |
0円 |
4月から翌年3月までを1年間(12か月分)として、年間保険料額が計算されます。年度途中で加入された場合は、加入月分から計算され、年度途中で資格を喪失された場合の喪失月分は計算されません。
後期高齢者医療保険料の軽減
次の所得等の被保険者は、均等割額が軽減されます。
「給与所得者等」とは、給与所得又は公的年金に係る雑所得がある方です。
| 軽減後の均等割額 | 世帯内の被保険者と世帯主の令和6年中所得の合計額 | |
|---|---|---|
| 世帯状況 | 計算方法 | |
| 7割軽減 14,886円/年 |
給与所得者等が1人以下の場合 | 43万円以下 |
| 給与所得者等が2人以上の場合 | 「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 | |
| 5割軽減 24,810円/年 |
給与所得者等が1人以下の場合 | 「43万円+30万5千円×世帯内の被保険者数」以下 |
| 給与所得者等が2人以上の場合 | 「43万円+30万5千円×世帯内の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 | |
| 2割軽減 39,696円/年 |
給与所得者等が1人以下の場合 | 「43万円+56万円×世帯内の被保険者数」以下 |
| 給与所得者等が2人以上の場合 | 「43万円+56万円×世帯内の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 | |
※所得が公的年金の場合は、軽減判定の際に限り、15万円を限度として控除があります(昭和35年1月1日生以前の方)。
※軽減判定の際には、「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
※所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。
※軽減判定は、賦課期日(令和7年4月1日又は資格取得日)時点で行われます(世帯状況や広島県内の住所に異動があっても再判定は行いません。)。
後期高齢者医療保険料の納め方
保険料は原則として受給する公的年金から差引されます。
【特別徴収】
次に該当する方などが、特別徴収になります。
(1)公的年金受給額が年額18万円以上の方
(2)介護保険料が公的年金から差引され、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が公的年金受給額の2分の1以下の方
年6回の公的年金支給日に保険料が差引されます。
年金を複数受給されている方は、年金の種別により、優先順位があります。
4月[1期]、 6月[2期]、 8月[3期]・・・仮徴収
前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。
なお、「仮に算定された保険料額」は、前年度の本徴収時に確定した2月[6期]分と原則同額です。
10月[4期]、 12月[5期]、 2月[6期]・・・本徴収
確定した年間保険料額から仮徴収分を差引いた残りの額を、3回に分けて納めていただきます。
【普通徴収(納入書払い、口座振替)】
町から送付する納入書又は口座振替により保険料を納めていただきます。
次のいずれかに該当する方は、普通徴収になります。
・特別徴収の事由に該当しない方
・75歳になったばかりの方や、他の市町から転入したばかりの方
後期高齢者医療制度に加入前に健康保険組合等の被扶養者だった場合で、保険料が減額されていないとき
後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等(国保及び国保組合は除く。)の被扶養者であった被保険者については、所得割額の負担はなく、資格取得後2年間を経過する月までに限り、均等割額が5割軽減され、令和7年度の年間保険料額は24,810円となります。ただし、均等割額の7割軽減に該当する方は、そちらが優先されます。
健康保険組合等から後期高齢者医療広域連合に通知がなく、保険料の軽減(所得割額の負担なし、均等割額5割軽減)がされていないときは手続が必要です。
保険料の計算方法について、詳しくは広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
【申請に必要なもの】
- 被扶養者届出書 [Wordファイル/42KB]
- 健康保険組合等の被扶養者であったことがわかる資格喪失証明書
- 資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 本人であることを証明するもの
- 委任状(代理人が申請する場合 [Wordファイル/33KB]
火災や災害等の被害、事業の休廃止等で収入が著しく減少したとき
医療機関で支払う一部負担金の減免、保険料の減免又は徴収猶予を受けることができる場合があります。
申請については、健康保険課へお問合せください。
保険料の減免について
後期高齢者医療保険料の納付方法を納入書から口座振替に変更したいとき
世羅町内の金融機関(尾道市農業協同組合、もみじ銀行、広島銀行、両備信用組合、ゆうちょ銀行)に口座振替依頼書を備え付けています。
通帳と通帳の届出印を持って、ご希望の金融機関の窓口で手続をしてください。
おおむね、手続をされた月の翌月から口座振替を開始します。
後期高齢者医療保険料の口座振替を廃止したいとき
口座振替を廃止したいときは届出をしてください。
【申請に必要なもの】
- 口座振替廃止届出書 [Wordファイル/42KB]
- 資格確認書
- 印鑑
後期高齢者医療保険料を特別徴収(公的年金から差引)から普通徴収(口座振替)に変更したいとき
保険料の納め方を特別徴収(公的年金から差引)から普通徴収(口座振替に限る。)に変更することができます。変更するには、町への申請が必要です。手続方法等、詳しくは、健康保険課へお問合せください。
※口座からの支払い開始月は、申出の時期により異なります。
※特別徴収から納入書払いに変更することはできません。ご了承ください。
※口座振替では確実な納付が見込めない方については、口座振替への変更が認められない場合があります。
書類の送付先を変更したいとき
入院や入所等の理由により書類の送付先変更を希望されるときは、届出をしてください。
-
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
※郵送で提出される場合は提出される方の身分証明書(運転免許証等)の写しの添付をお願いします。
【注意事項】
・設定にあたり、宛名には様方などが入ります。
・広島県広島市~区~町●●番地 △△様方✕✕様 のような表示になりま
・宛名に対象の方の氏名を載せないようにするといったことはできませんので、ご注意ください。
・転居や設定が不要になったときには、設定の変更や解除を申出ください。
・申出書に記載の業務のうち、設定したい業務が複数あるときは、提出先はいずれかの担当窓口で構いません。受付をした担当から、各業務担当に申出書の回付をさせていただきます。