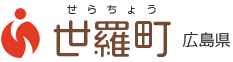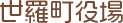本文
国民健康保険・受けられる給付
国民健康保険(国保)の給付
国保の資格確認書等で医療機関等にかかると、かかった医療費の一部の負担(一部負担金)で医療を受けられます。
受けられる医療
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院及び看護
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)及び看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
医療費の負担割合
| 小学校入学前 | 小学校入学後 70歳未満 |
70歳以上75歳未満 | |
|---|---|---|---|
| 2割 | 3割 | 2割 | |
| 3割 現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上) |
|||
高額療養費
国保の被保険者が同じ月に、同じ医療機関に支払った医療費(入院・通院・歯科別)の負担が次の表の限度額を超えたとき、健康保険課に申請すると超えた部分の払戻しを受けられます。入院時食事負担金、保険適用外の費用は高額療養費の算定から除きます。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の場合
| 適用区分 | 所得区分※1 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降)※2 |
|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 140,100円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 93,000円 |
| ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) | 44,400円 |
| エ |
210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 判定に使用する所得は、国保被保険者の総所得金額等から基礎控除額を差引いた額です。
住民税非課税世帯の判定は、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税であることが要件です。未申告者が世帯にいる場合の適用区分は「ア」の判定となります。
※2 過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あれば4回目以降の限度額が適用されます。
70歳以上の場合
| 適用区分 | 所得区分 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降)※2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 外来+入院 (世帯ごと) |
||||
| 現役並み所得者 | III | 課税所得 690万円以上の方 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
| II | 課税所得 380万円以上の方 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
| I | 課税所得 145万円以上の方 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
| 一般 | 課税所得 145万円未満の方 |
18,000円 ≪年間の上限144,000円≫※1 |
57,600円 | ||
| 住民税非課税世帯 | 低所得者II | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | 左記と同額 |
| 低所得者I | 住民税非課税世帯 (年金収入80万6,700円以下など) |
15,000円 | |||
※1 年間とは、8月から翌年7月までの1年間です。
※2 過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あれば4回目以降の限度額が適用されます。
高額療養費の申請に必要なもの
- 資格確認書又は資格情報のお知らせ
- 預貯金通帳など(世帯主名義のもの)
- 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの
入院時の食事代
入院中の食事代は、1食につき次の負担となります。
| 所得区分 | 食事代(1食当たり) |
|---|---|
| 住民税非課税世帯(区分オ)※1 | 240円 |
|
住民税非課税世帯(区分オ) (過去12か月の入院日数が90日を超える場合)※2 |
190円 |
| 上記以外の世帯 | 510円※3 |
| 所得区分 | 食事代(1食当たり) |
|---|---|
| 低所得者I ※1 |
110円 |
|
低所得者II ※1 |
240円 |
|
低所得者II (過去12か月の入院日数が90日を超える場合)※2 |
190円 |
| 上記以外の世帯 | 510円※3 |
※1 医療機関においてオンラインで区分が確認できない場合、健康保険が発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
※2 適用については必ず申請が必要です(長期認定)。申請日から軽減されます。
※3 指定難病又は小児慢性特定疾病の方は300円となります。
療養病床に入院する場合の食費・居住費
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ次の標準負担額を負担します。
| 所得区分 | 食事代(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
|---|---|---|
| 低所得者I | 140円 | 370円 |
|
住民税非課税世帯(区分オ) 低所得者II |
240円 | 370円 |
|
上記以外の世帯 |
510円 | 370円 |
窓口での支払が限度額までになるとき
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で受診、又は医療機関等でオンライン資格確認が可能な場合は、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても、医療機関等の窓口での支払は自己負担限度額までとなります。マイナ保険証で受診しない場合は、申請により交付します。
申請に必要なもの
- 資格確認書又は資格情報のお知らせ
- 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの ※長期認定の申請には次のものも必要です。
- 領収書など(入院日数が90日を超えることがわかるもの)
高額医療・高額介護合算制度
年間の医療費が高額になった世帯に介護サービス利用者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、年間の自己負担を合算して次の限度額を超えた場合は、その超えた額が申請により支給されます。年間で国保か介護保険どちらかの自己負担が全くない世帯は支給対象外です。
合算した場合の限度額は次のとおりです(年額:8月~翌年7月)。
70歳未満の場合
| 所得区分 | 限度額 |
|---|---|
| 901万円超 (ア) | 212万円 |
| 600万円超~901万円以下 (イ) | 141万円 |
| 210万円超~600万円以下 (ウ) | 67万円 |
| 210万円以下 (エ) | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 (オ) | 34万円 |
70歳以上75歳未満の場合
| 所得区分 | 限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | III | 課税証明690万円以上の方 | 212万円 |
| II | 課税所得380万円以上の方 | 141万円 | |
| I | 課税所得145万円以上の方 | 67万円 | |
| 一般 | 課税所得145万円未満の方 | 56万円 | |
| 低所得者II | 住民税非課税世帯 | 31万円 | |
| 低所得者I |
住民税非課税世帯(年金収入80万6,700円以下など) |
19万円 |
|
厚生労働大臣が指定する特定疾病について
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の方は、1つの医療機関で1か月間に10,000円(※1)までの負担となります。この場合、「特定疾病療養受領証」が必要となりますので、健康保険課にご相談ください。
申請には医師の診断書、資格確認書又は資格情報のお知らせ、世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるものが必要です。
※1 人工透析が必要な慢性腎不全の方で70歳未満の上位所得者については、1か月間に20,000円までの負担となります。
国保で受けられない・又は制限される診療
- 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
- 健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正
- 仕事上のケガや病気、労災保険の対象になる場合
- けんかや泥酔などによるケガや病気
- 医師の指示に従わなかったとき
- 犯罪を犯した時や、故意による病気やケガ
払戻しが受けられるもの(療養費の支給)
次のようなとき、国保(健康保険課)に申請し、認められると保険給付分の給付を受けられます。
| 払戻事由 | 必要なもの |
|---|---|
| 急病などでやむをえず資格確認書等を持たずに診療を受けたとき | 診療報酬明細書(レセプト)、領収書、資格確認書又は資格情報のお知らせ、預貯金通帳(世帯主名義のもの) 、対象者のマイナンバーが確認できるもの |
| 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき | 補装具必要証明書、装具装着証明書(保険医)、領収書、資格確認書又は資格情報のお知らせ、預貯金通帳(世帯主名義のもの)、対象者のマイナンバーが確認できるもの |
| 海外で診療を受けたとき (治療目的で渡航した場合を除く) |
診療内容の明細書と領収明細書(原本及び日本語に翻訳してあるもの)、資格確認書又は資格情報のお知らせ、海外の医療機関等に照会する同意書、預貯金通帳(世帯主名義のもの)、パスポートの写し 、対象者のマイナンバーが確認できるもの |
その他の給付
被保険者が出産したときや死亡したときは、健康保険課に申請してください。