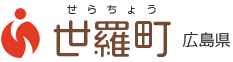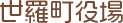本文
鉄製十二灯明台
更新日:2022年8月12日更新
印刷ページ表示
世羅町指定重要文化財(美術工芸品/工芸品)
鉄製十二灯明台(てつせいじゅうにとうみょうだい)
昭和40年(1965)10月30日指定
仏前に灯明を献ずる14箇の皿付き鉄製灯明台。灯明は神仏に供える灯火の事で、仏教ではサンスクリット語の「ディーバ」を和訳し、意味は闇を照らす知恵の光とされ、お釈迦様の教えを表すとされます。
今高野山龍華寺に伝わる灯明台は、直径36cm円盤状の台を三脚で支え、その上に中央にまっすぐに鉄棒を1本、それを取り巻くように鉄棒を直径48~51cmの輪状にしたものを合わせている。最上部には鉄製の灯明皿と鉄芯をしつらえ、中心の鉄棒に3個、周辺の輪に10個の小さな鉄製の輪がおそらくロウ付けにより付けられている。この小さな鉄輪に灯明皿を置いて使用したものを思われる。
三脚の一つに「大旦那藤原氏和知右衛門太夫豊将」とあり、他の一脚に「弘治二年丙辰三月吉日(1556)」、残りの一脚に「三原之住倫 ■■■作」と読める陰刻銘がある(製作鍛冶銘と推定)。甲山城主和智豊将が一山を復興した時の記念として寄進したものであることがわかる。県内的に見ても、紀年銘のある鉄製灯明台は貴重である。
「三原之住」と判読した銘は、十二灯明台を製作した鍛冶と推定されるが文字数を含め作者名は解読できていない。