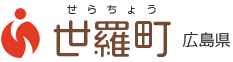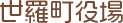本文
三鈷・独鈷
更新日:2022年8月12日更新
印刷ページ表示
広島県重要文化財(美術工芸品/工芸品)
三鈷(さんこ)
昭和28年(1953)6月23日指定
独鈷(とっこ)
昭和28年(1953)8月11日指定
今高野山龍華寺に伝わる密教法具のひとつ。平安時代に空海・最澄などによって中国から請来されたといわれる密教(真言宗・天台宗)の修法には、金剛杵(こんごうしょ)・金剛鈴・金剛盤・輪宝(りんぽう)・羯磨(かつま)・火舎(かしゃ)・花瓶・六器ほか多くの法具が用いられる。法具は,心中の煩悩をくだき仏性の智光をあらわす意味で用いられるとされる。
今高野山龍華寺に伝わる三鈷は金銅製で、装飾性も高い。長さ20cmで、中央部分の鬼目(きもく)と呼ばれる部分が大きく、両側の鈷と呼ばれる部分の先端部分は鋭くとがり、中央部分は大きく張った、鎌倉時代の特徴を有するすぐれた作品である。
一方の独鈷も金銅製で、同じく装飾性も高い。長さ20cmで、中央部分の鬼目(きもく)と呼ばれる部分が大きく、両側の鈷と呼ばれる部分の先端部分が鉾状にとがった鎌倉時代の特徴を有するすぐれた作品である。