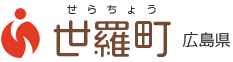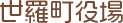本文
金銅製仏舎利塔
更新日:2022年8月12日更新
印刷ページ表示
世羅町指定重要文化財(美術工芸品/工芸品)
金銅製仏舎利塔(こんどうせいぶっしゃりとう)
昭和59年(1984)5月15日指定
仏舎利塔とは、仏舎利(釈迦の遺骨)を納めるとされる仏塔で、仏塔の原型であるインドの「ストゥーパ」の様式をそのまま模して造られ、構造物の上に相輪(そうりん)にをもつ。
今高野山龍華寺に伝わる仏舎利塔は、寺伝によると慶長11年(1606)、芸備大守福島正則が領国巡視の折、当地に来て安楽院に止宿し、寺領として今高野山へ寺領50石を寄進した際に、奉納したものと伝えられている。金工の粋をつくした作品として貴重である。
高さ48.5cmで、多宝塔風の造りをしている。塔身部分には四方に観音開きの扉があり、扉を開くとガラス板の壁がある。その内部は三層に仕切られ、舎利仏はその二層目に収められている。相輪の宝珠裾からは宝鎖(ほうさ)と呼ばれる鎖が四方の軒先に繋がっている。細部にわたり彫金が施され、装飾性の高い造りとなっている。塔の台座は木製で、一部が欠損している。
奉納者とされる福島正則は尾張国の生まれで、幼少から豊臣秀吉に仕えて各地を転戦した武将。秀吉の死後、関ヶ原の戦いで東軍の主力として活躍し、戦後広島城主として49万8000石を領有した。城主が浅野氏に代わっても今高野山の俸禄米は安堵され、幕末まで続いた。