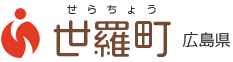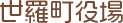本文
蔵骨器
更新日:2021年9月24日更新
印刷ページ表示
蔵骨器
世羅町宇津戸の下仮屋で出土した蔵骨器は、須恵器質の壺形土器で、おそらく火葬後の骨を納めていたものと考えられている。形式からみて平安時代のものと考えられる。ロクロを使用した丁寧な成型で、平坦な底面ゆるやかに外側に広がり、中央よりもやや上方に肩を作る。頸部を細くしぼり、口縁部にむけてやや外側に反らせている。もともとは蓋もしくは受けとなる坏が伴っていたと考えられるが、発見されていない。また出土状況も不明である。埋葬施設などの遺構も確認されていない。周辺には池の奥古墳(年発掘調査実施)などの古墳も存在するが、時代が異なる。
一方、世羅町赤屋の廃明覚寺跡宝篋印塔(町指定重要文化財)の塔の下から出土した蔵骨器は、体部の外面に格子目タタキが施された亀山式と呼ばれる甕で、底が欠けている。体部と口縁部の屈曲は緩やかで、頸部も広く、口縁部も長めに作られている。廃明覚寺跡宝篋印塔は、南北朝~室町時代の特徴を持つ大型の宝篋印塔で、その下から出土したことから、同時代の蔵骨器と推定される。
このほか町内では、世羅町指定重要文化財の光明寺古墓(世羅町堀越)からも蔵骨器と考えられる須恵質の甕が出土している。