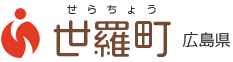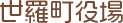本文
今高野山城出土品
更新日:2021年9月24日更新
印刷ページ表示
今高野山城出土品
今高野山城は、永正(1504~1520)の頃、山内氏が築き、その跡を天文(1532~1554)の頃から天正10年(1582)まで和智氏が居城したと思われている。守護山名俊豊が山内直通(豊成子)に大田庄本郷・寺町を明応3年(1496)にあてがっていることから、その頃の築城も推定される。今高野山城は、主郭は山頂を削平しているがカブト岩(エボシ岩ともいう)と呼ばれる巨岩が突出している。主郭群の北側に2段、南側には2段の郭がある。西側には小規模な帯郭群が見られる。主郭群の北方に出丸があるが、戦時中防空監視哨が設けられたため遺構が破壊されている。
昭和62年(1987)には展望台建設に際して、二の丸跡の発掘調査が実施され、白磁片、土師質土器片、備前焼水甕片のほか中国製の古銭が出土した。
また、本丸跡では刀子や雷鉢片、土師質土器片などが表面採取されている。
尚、言い伝えによると、今高野山の主郭や帯郭に使われていた石垣は明治初年頃に下へおろされ、極楽寺前の川底や石垣等に使われたとのことである。