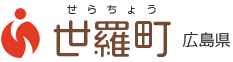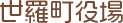本文
梵鐘
更新日:2021年9月24日更新
印刷ページ表示
世羅町指定重要文化財(美術工芸品/工芸品)
梵鐘
昭和59年(1984)5月15日指定
梵鐘とは、一般的には鐘・釣鐘と呼ばれているもので、仏教法具として仏教とともに大陸から伝来した。時を知らせたり儀式の時などに鐘楼に吊って撞木で撞き鳴らして使用するものである。重く余韻のある響きが特徴で一般には大晦日に撞く「除夜の鐘」で知られている。
指定となっている梵鐘は、備後国の鋳物師総大工職として代々勢力をふるってきた宇津戸の丹下氏の鋳造したもので、県内に現存する在銘の丹下氏の銅鐘の中では最古の作である。和鐘形式で、高さ1.3m、口径76cm。鐘には檀主として、町年寄(甲山町の役人層)であった渋谷・広瀬・小川氏の名前のほか、制作者名(橘朝臣丹下甚右衛門)と制作年も陰刻されており、寛文7年(1667)に制作されたことがわかる。
この梵鐘は太平洋戦争中の金属不足の折、軍需物資として供出にあいかけたが、地元住民の請願が聞き遂げられて遺された貴重な梵鐘である。